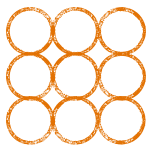Thread by Thread
プレイリー・スチュアート・ウルフ


料理人は走る
「ご馳走さまでした」。それが特別な料理屋でも、家の食卓であっても、私たちはこの言葉で食事を終える。一食への感謝を、馬を駆る人を思い浮かべる言葉で表す。それは食事自体だけでなく、その食事のために「走り回って」費やされた労力への感謝でもある。
もしも時代が違っていたら、料理長・松本進也は、鞍を付けた馬にまたがって行ったかもしれない。いまの彼はハンドルを握り、車を走らせる。大原へ、太い象牙のような筍を集めに向かうかもしれないし、尖った草の葉の間からこごみのうず巻きが伸びてきている川のほとりを歩きに行くかもしれない。「毎日、走り回るんです」と彼は言う。「素材を自分でとりに行って、それを自ら調理する。わざわざそこに行って、いちばんいいものをとってくる。その気持ちが、ご馳走です」

春には猛スピードで新鮮なものが芽吹いてくる。料理人は追いつくのがやっとだ。竹やぶに向かう途中、イタドリの小さな茂みがあった。片手で車を道路脇に寄せながら、もう片方の手でダッシュボードから鋏を取り出すと、車から飛び出して摘み始めた。長い緑の茎 には紅紫の斑があり、ふっくらとしている。「剥いて、焼いても美味しいし…和えもんにしても、めちゃくちゃうまいんです」確かに剥いたほうがいい。このタデ科の植物をそのまま生で噛むのは、さとうきびを齧るようなものだ。身と汁にはルバーブのような酸味があって柑橘系の香りも感じるが、皮は繊維質で硬い。
先へ進んだところにある休耕地で、彼はセリを探している。林の中からカエルの合唱が聞こえる。猪がやってきたあとなのか、柔らかい芽は少ししか残っていない。「野生のもんだから、香りが強いですね」ほんのひと掴みあれば十分だろう。
さらに道を進んだ先で、彼はその日の筍の収穫に目を通す。ナイフを手に、若い筍を細く裂いて口に入れ、自然の甘みと身の密度を見極める。「筍屋さんに任せてもいいんですが… 僕らには、舌の感覚がある。舌で味の本質がわかるというのは、たぶん料理人だけだと思います。これ、という食材がここにあるから、それをめがけてここまで来るのが、僕の仕事なんです。」
午前中も半ばを過ぎている。調理場に戻る時間だ。料理をして、今日のお客さまをお迎えするのだ。お客さまから帰り際に「ご馳走さまでした」の一言を聞ければ、料理人は微笑み、次の朝まで心安らかに休むことができる。