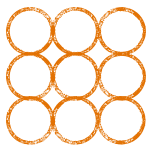Thread by Thread
プレイリー・スチュアート・ウルフ


ひと粒から生まれる恵み
和久傳のふるさと、丹後半島の山の奥、地形が許す限りいちばん高いところに、棚田が作られている。そのさらに奥、野生のイノシシや鹿が徘徊する大きな森にある滝から、冷たい澄んだ水が流れ出て、田んぼを満たす。7月の高い空の下、田んぼの浅い水の中には、無数のおたまじゃくしが泳ぎ回っている。夏が進むにつれて緑は濃くなり、秋が近づくと重たい稲穂が緑の葉の間からこうべを垂れる。
おたまじゃくしはカエルになり、実りを食い荒らすイナゴやカメムシが好物だ。この田んぼの責任者であり、米を種から収穫まで導く本田進が、イナゴを手で捕まえる。こいつらと雑草とが、彼にとって手が掛かる。カエルと蜘蛛は、イナゴを採ってくれてありがたい。
25年ほど前、本田はこの田んぼを無農薬有機栽培に変えた。自分の幼い娘が、ひどいアトピーに苦しんでいたときだった。医者は簡単には治らないものだといい、それは父親としては受け入れられることではなかった。彼は、人間の体は自らが食べるものでできているのだから、娘の状態は彼女が食べた食品中の有害なものがもたらしているのではないかと推論した。農薬の影響も、そのひとつ。収穫量が減ること、そして雑草や虫との戦いを受け入れなければならなかったが、彼の決心は固かった。いま、彼のイセヒカリの田んぼは、見事に逞しく育っている。


イセヒカリの伝説は、この小さな島国の歴史と心に連なっている。この国では何世紀にもわたって気まぐれな神々が天候を操ってきた。三重県の伊勢神宮を強力な台風が襲い、神聖な田を壊滅させた後、痛んだ稲の中の数本がわずかに生き延びているのが見つかった。果てしない損害の中の、小さな恵み。この奇跡の稲はその後、種の名前であるコシヒカリではなく、特別に「イセヒカリ」と呼ばれることに決められた。
イセヒカリが伊勢神宮から和久傳まで辿り着き、そして本田の田んぼに植えられたことも、恵みだった、と女将の桑村祐子は言う。あるとき、数本の稲穂が、大切なお客さまから贈られた。それは、その頃彼女が感じていた、料亭の食事はただ美味しいという以上のものでなければならないという気持ちと響き合った。匿名の、物語のない素材から離れること。健やかなエコシステムを作ろうとしている生産者たちの、育ちつつあるコミュニティに参加すること。それは、彼女の京都の料亭が、料理の核となる素材との関係を深め、食事に訪れるお客さまに滋養のあるより良いものを提供できることにつながっていく。


種には無限の可能性がある。手のひらに持てば、文字通り未来を手にすることができる。ひと粒の米から何百もの米粒が生まれ、程なく本田は和久傳のためにまとまった量のイセヒカリを作りだせるようになっていた。いま、毎年5月に、和久傳の従業員とゲストたちとが京都から丹後の山を訪れる。半日、共に腰をかがめ、泥の中に苗を植える。夏の暑い日々から、秋の収穫を迎えるまで、毎週従業員が丹後を訪れて田んぼの世話を手伝う。
京都の厨房では、料理人が、自らが植えた米から作った麹を扱う。食事の席ではサービスのスタッフがお客さまに酒を注ぎながら、その原料の米が育った田んぼの雑草を自分たちで抜いた話をしている。一年を通して、米粒の一生が、京都の料亭と丹後とをつないでいる。