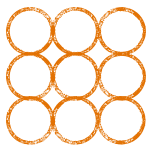Thread by Thread
プレイリー・スチュアート・ウルフ


舵をとる
田中敏弘は、頭上でしなる竹の竿からマリオネットのように吊るされた大きな木枠を掴む。そして大きく息をして、その下にある液に差し込む。コウゾの皮からとった繊維を水で伸ばした溶液を、木枠の中のスクリーンに広げる彼の動きは音楽的だ。
「若い時には漉き方、水の動かし方、そればかりに目をとられていて。その理想だけを追い求めていました」と彼は言う。「今は 感じながらやっている」からだの動きと液体のさざ波とのリズムが合っている。「漉いているときに、水とぴったり動きがいっしょになる時があります。その時ほど、ほんとうに気持ちがいい、からだが楽な時はないですね」 彼は木枠を支えで開き、新しく出来上がった一枚の和紙が空気に触れて落ち着くように、少し間をおく。田中の職人としての進化が、この束の間に凝縮されている。

田中は妻と高齢の両親と共に、丹後半島に一時は数百もあった和紙工房の最後の一軒を営んでいる。この地域が時代と共に変わっていくのを見てきた生き証人だ。それは全国的な流れでもあった。大量の海外産のコウゾ繊維が輸入され、国内の生産者は立ち行かなくなった。この地域の気候はコウゾの生育には適していたが、生産は先細っていった。全国で、輸入された素材による製紙が行われ、地域ごとの和紙の特徴が消滅するさまに気づいて、彼は将来を再考せざるを得なくなった。「家族だけでやっている小さいところで生き残っていこうと思いますと、やはり他にはないものをつくる必要がありまして。それは何かと思いますと、この土地でコウゾを育てて、この土地の水で紙にする。これは他には絶対にできない、絶対に真似のできないものなんです」
コウゾは持続可能な作物だ。冬にはすべての枝を刈り取り、それが次の夏にはまた豊かに再生する。丈夫なコウゾの畑が育つには10年かかるが、根気よく働いてきたことで、今は一年を通して自らの畑で育った素材だけで紙をつくることができる。彼自身、コウゾを育てることに多くの時間と努力を費やしたことで、ものの見方が大きく変わった。「素材のことをまず考えるようになりました。自分のところで育ったコウゾがもっている性質を生かして、それを引き出してやって最高の紙を漉くことを考えています」と彼は説明する。力を抜き、一度は完全に支配しようとしたプロセスを、導くようにとらえ始めた。「水を動かすんじゃなしに、水の動きに僕が合わせるというか。そうしたら無理のない表情がそこに生まれるんじゃないかというふうに思いまして」そうして、漉き上がった和紙を頭の上で回転させて積み置く前に、一瞬止まって呼吸させることにしたのだ。


何世紀も続く家族の仕事は船のようだ。順に次の世代が舵をとる。五代目の舵をとる田中は先人たちの経験から学んで、自分の時代の課題を乗り越えようとしている。彼の祖父は一つの商品を生産した。それは薄いガーゼのよう な和紙で、漆職人が漆を塗る前に濾すために使われた。しかしその需要は減 り、彼の父親の時代には色とりどりに染められた和紙を使った製品が日本中 の百貨店に並んだ。それは彼の家族の製品の名を広めたが、百貨店の時代は終わろうとしている。田中は習字用と日本家屋用に、彩色しない和紙を自給自足でつくれるように進めてきた。彼の紙は桂離宮や京都御所を始め、様々な歴史的建造物の修復や修理に使われている。「伝統を守るということはただ単に昔からずっとあったものをその次へ伝えて行くものではないと思っています。その代その代で時代にあったもの、新しいものをつくりだして、次の代にバトンを渡して行くことが、伝統を守るということだと思います」
田中のつくる、柔らかな象牙色の光を通す和紙はあたたかみがあり、強く、柔軟性があって、何世紀もの命を持っている。自分の紙が長く残ることはわかっていても、彼の持つ技術がこれからどうなっていくかはわかっていない。彼は次の世代に確かに技を伝えるという一つのステージを受け持っているに過ぎない。「僕らの世界には完成ということ、完璧ということはまずないですから。これから僕が60になった時の紙、70になった時の紙を、後から見て、あ、ちょっとずつだけどよくなってると思える、最終的にそうなればいいなと思います」